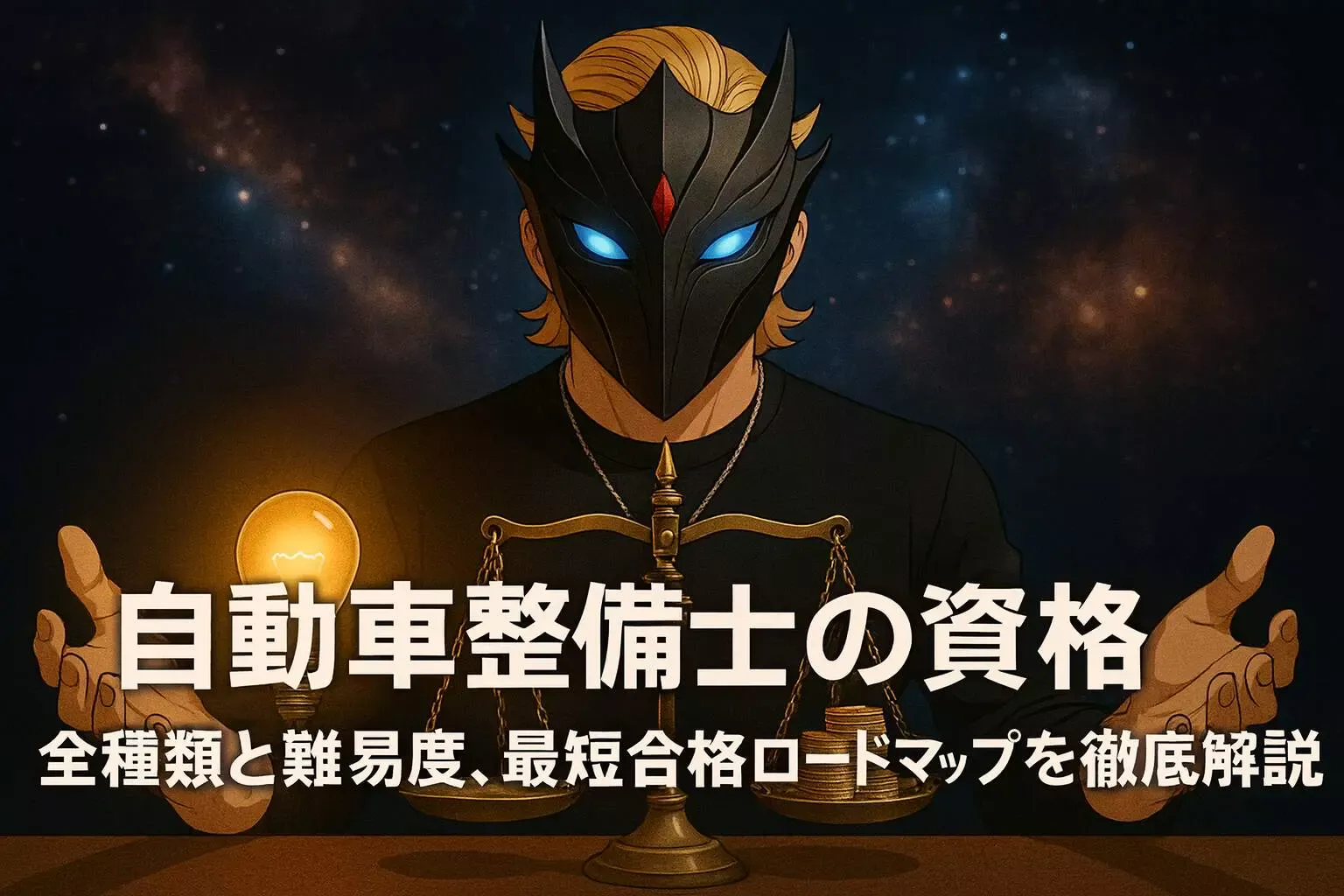これから自動車整備士はどうなる?資格制度や法改正で俺が予想するミライ

16年現場を見てきた一級整備士が語る業界の転換点
俺は自動車整備士として16年間現場で働き、国家一級整備士の資格を取得した。現在はマーケッターとして活動しているが、車への愛情は変わらず、将来的には趣味の領域で自動車検査員の資格取得も考えている。そして最終的には自分の整備工場を立ち上げ、現場で車を修理する仕事から離れるつもりはない。
なぜ今、この記事を書くのか。それは2026年7月8日に控える自動車整備士制度の大幅改正が、業界にとって歴史的な転換点になると確信しているからだ。
この16年間で俺が目の当たりにしてきた業界の変化は凄まじい。ハイブリッド車が当たり前になり、電気自動車が街を走り、自動ブレーキや車線維持システムが軽自動車にまで搭載される時代。一方で、整備士不足は深刻化し、若手の確保は困難を極めている。
しかし、俺はこの状況を悲観していない。むしろ、技術の高度化と制度改正により、自動車整備士の価値と将来性は飛躍的に向上すると考えている。2026年の制度改革は、まさにその転換点なのだ。
- 自動車整備士の現状と課題:深刻な人材不足の実態を数字で検証
- 2026年自動車整備士資格制度改正の全貌:何が変わるのか徹底解説
- 自動車整備士資格取得のハードルが下がる:実務経験短縮の影響
- 自動車検査員資格の価値が急上昇:自動運転時代の必須スキル
- 電動車・EV時代に求められる自動車整備士のスキル
- AI・自動運転技術と自動車整備士の共存:なくならない仕事の理由
- 待遇改善の兆し:自動車整備士の年収アップ戦略
- 地域の整備工場が生き残る方法:個人事業主の視点から
- 自動車整備士資格の取得戦略:効率的なキャリアパス設計
- 整備工場経営者が知っておくべき法改正ポイント
- 俺が予想する自動車整備士の未来像:2030年代のシナリオ
- これから自動車整備士を目指す人へのメッセージ
自動車整備士の現状と課題:深刻な人材不足の実態を数字で検証
まず現実を直視しよう。日本自動車整備振興会連合会の「自動車整備白書2023年度版」によると、整備士数は2011年度の34万7,276人をピークに減少を続け、2023年度には33万1,255人まで減少した。実に10年余りで約1万6,000人、率にして約4.6%の減少だ。
一方で、自動車保有台数は増加を続けており、2024年3月末で約8,257万台に達している。つまり、整備対象となる車は増えているのに、整備する人は減っているという構造的な問題が発生している。
整備工場の約5割が「人手不足を感じている」と回答している統計もあり、現場の実感として、この数字は決して大げさではない。俺が働いてきた現場でも、求人を出しても応募が来ない、来ても長続きしないという状況が常態化していた。
人材不足の原因は複合的だ。第一に少子化による労働人口の減少。第二に若者の車離れ。昔は車への憧れから整備士を目指す若者が多かったが、今は車を所有しない若者が増えている。第三に職業選択の多様化。IT関連職種など、より魅力的に見える職業選択肢が増えた。
そして最も深刻なのが、自動車技術の進歩による整備項目の増加と複雑化だ。従来のエンジン、トランスミッション、ブレーキ、サスペンションといった機械的な部分に加え、電子制御システム、ハイブリッドシステム、先進安全装備の整備知識が必要になった。学ぶべき範囲が飛躍的に広がったのに、給与水準は他業種と比較して低いままだった。
これらの課題が相互に作用し合い、整備士不足という悪循環を生み出している。しかし、この状況こそが、今後整備士の価値向上につながる要因でもあるのだ。
2026年自動車整備士資格制度改正の全貌:何が変わるのか徹底解説
2026年7月から公布と施行される自動車整備士資格制度の改正は、まさに時代の要請に応えるものだ。現行制度は1980年代の技術水準を前提に作られており、現在の高度化した自動車技術に対応しきれていなかった。
最も大きな変更は、資格の種類統合だ。現行制度では、3級から2級、1級まで各級で「ガソリン」「ジーゼル」「シャシ」「二輪」の4種類に分かれていたが、新制度では「総合」と「二輪」の2種類に統合される。
この統合の背景には、現代の自動車がガソリンエンジンとディーゼルエンジンの境界を越え、ハイブリッドシステムや電子制御技術が複合的に組み合わされているという現実がある。もはや「ガソリン専門」「ディーゼル専門」という区分では対応できないのだ。
新制度では、2級自動車整備士・総合の資格に、これまで1級にのみ求められていた電子制御装置に関する知識・技能が含まれる。これは現場で働く俺たちにとって、非常に理にかなった変更だ。今や軽自動車でも電子制御スロットル、ABS、エアバッグ、先進安全装備が当たり前に搭載されている。2級整備士がこれらの知識なしに現場で働くのは現実的ではない。
特殊整備士についても大幅な見直しが行われる。自動車電気装置整備士は「自動車電気・電子制御装置整備士」に、自動車車体整備士は「自動車車体・電子制御装置整備士」に名称変更される。これも電子制御技術の重要性を反映した変更だ。
また、1級整備士試験の口述試験が廃止される。この試験は形骸化が指摘されており、実務に即した内容ではなかった。新制度では、ユーザーとの対話スキルを実技試験に組み込むことで、より実践的な能力評価が行われる。
これらの変更により、整備士資格はより実務に即した、現代の自動車技術に対応できる資格体系に生まれ変わる。現場で働く整備士にとって、取得する価値のある資格になるのだ。
自動車整備士資格取得のハードルが下がる:実務経験短縮の影響
制度改正で特に注目すべきは、実務経験年数の大幅短縮だ。2級自動車整備士の受験に必要な実務経験が3年から2年に、3級は1年から6ヶ月に短縮される。これは若手整備士の確保という観点から、非常に重要な変更だ。
俺が整備士になった頃を振り返ると、高校卒業後に3級を取得し、その後3年間の実務経験を積んで2級を取得するまでの道のりは確かに長かった。特に若者にとって、資格取得までの期間が長いことは大きなモチベーション低下要因だった。同期の中にも「3年も待てない」と言って他業界に転職した者がいる。
実務経験短縮のもう一つの背景は、整備作業の性質変化だ。従来の機械中心の整備では、実際に手を動かして覚える経験の積み重ねが重要だった。しかし現在は、電子制御システムの診断や設定作業など、座学で得た知識がより重要になっている。故障診断においても、経験による勘よりも、システムの理解に基づく論理的思考が求められる場面が増えた。
また、電気・電子系の教育課程を修了した受験者についても、機械系学生と同様に実務経験が短縮されるようになった。これは時代の要請に合った変更だ。自動車の電子化が進む中、電気・電子分野の知識を持った人材の価値は高まっている。
特殊自動車整備士についても、必要実務経験が2年から1年4ヶ月に短縮される。タイヤ整備士、電気・電子制御装置整備士、車体・電子制御装置整備士といった専門分野への参入障壁が下がることで、より多くの人材が専門性を身につけられるようになる。
この実務経験短縮により、高校生が整備士を目指すケースでは、最短で卒業から2年6ヶ月で2級整備士資格を取得できるようになる。これは人材確保の観点から非常に大きな効果が期待される。
自動車検査員資格の価値が急上昇:自動運転時代の必須スキル
俺が今、趣味の領域で自動車検査員資格の取得を検討している理由の一つが、2026年7月8日公布される新たな規制だ。自動運転車(レベル3・4)の検査を行う自動車検査員は、1級自動車整備士資格を保有している者の中から選任しなければならなくなる。
これは自動車業界にとって画期的な変更だ。これまで自動車検査員は、2級整備士資格と整備主任者として1年以上の実務経験があれば教習を受講できた。しかし自動運転車に限っては、最高位の1級整備士資格が必須となる。
ただし、2030年4月1日施工時点で、二級自動車整備士は4年間は自動車の検査をすることが可能。
詳細は国交省の最新のアップデート解説を見てくれ。
自動運転車は文字通り「電子制御装置の塊」だ。LiDAR、レーダー、カメラなどのセンサー類、これらの情報を処理するECU(電子制御ユニット)、アクチュエーター類、そしてこれらを統合制御するソフトウェア。従来の機械的な検査では対応できない高度な電子システムの検査が必要になる。
1級整備士に求められる電子制御装置の深い知識と技能が、まさに自動運転車検査には不可欠なのだ。センサーの校正、ソフトウェアの更新確認、システム間の連携動作確認など、高度な専門知識なしには適切な検査ができない。
この規制により、1級自動車整備士の価値は大幅に向上する。自動運転車の普及が進めば進むほど、1級整備士資格を持つ検査員の需要は高まる。まさに希少価値の高い人材になるのだ。
検査員教習の受講条件は厳格だ。指定工場に勤務し、整備主任者として1年以上の実務経験を有し、直近の整備主任者研修を受講していることが必要だ。教習は通常5日間で行われ、最終日に修了試問がある。合格率は約50〜70%程度で、決して簡単ではない。
しかし、マーケッターとして培った論理的思考力と、16年の現場経験、そして1級整備士としての知識があれば、検査員資格の取得は十分可能だと考えている。自分の整備工場を立ち上げる際にも、検査員資格があることで指定工場としての運営が可能になり、事業の幅が大きく広がる。
電動車・EV時代に求められる自動車整備士のスキル
2035年までに新車販売の電動車100%を目標とする政府方針により、整備士に求められるスキルセットは劇的に変化している。俺がこの16年間で最も強く感じている変化の一つが、電動車整備技術の重要性だ。
ハイブリッド車(HV)の整備では、高電圧システムの安全確保が最優先となる。200V以上の高電圧回路を扱うため、感電事故のリスクが常に存在する。作業前の高電圧システム遮断、絶縁用保護具の着用、回路の絶縁抵抗測定など、従来のガソリン車整備では必要なかった安全手順が必須となった。
電気自動車(EV)では、さらに高度な知識が要求される。400V〜800Vという高電圧のバッテリーシステム、インバーター、モーター、充電システムなど、全く新しい技術領域だ。バッテリーの劣化診断、セル単位での容量測定、冷却システムの点検など、専用の測定器具と深い理解が必要だ。
燃料電池自動車(FCV)に至っては、水素という危険物を扱うため、さらに高度な安全管理が求められる。水素の漏れ検知、燃料電池スタックの点検、高圧水素配管の検査など、従来の整備技術とは全く異なる専門性が必要だ。
これらの電動車整備に共通するのが、電子制御システムの診断技術の重要性だ。故障コードの読み取りだけでなく、各システムの動作原理を理解し、データストリームを解析し、論理的に故障原因を特定する能力が求められる。
実際の現場では、電動車特有の故障モードも増えている。バッテリーの急速な容量低下、インバーターの異音、充電システムの不具合、回生ブレーキの効き不良など、従来のガソリン車では経験しなかった問題に対処しなければならない。
また、電動車の整備には特別教育の受講が義務付けられている。「電気自動車等の整備に係る特別教育」を修了することで、高電圧システムを扱う作業が可能になる。この特別教育は、労働安全衛生法に基づく法定教育であり、整備士としてのキャリアを続ける上で必須の資格といえる。
さらに、電動車の普及に伴い、充電インフラの整備・保守という新たな業務領域も生まれている。急速充電器や普通充電器の点検・修理は、従来の整備工場にとって新たな収益源となる可能性がある。
AI・自動運転技術と自動車整備士の共存:なくならない仕事の理由
「AIに奪われない仕事」として自動車整備士がよく挙げられるが、これは単なる希望的観測ではない。現場で16年働いてきた経験から、整備士の仕事がAIで完全に代替される可能性は極めて低いと確信している。
まず、故障診断における人間の判断力は代替困難だ。車の故障は一つの原因で起こることもあれば、複数の要因が複合的に絡み合っていることも多い。診断機器が示すデータを読み取り、お客様からの症状聞き取り、実際の車の状態観察、これまでの経験、そして時には直感を総合して原因を特定する。この過程は、極めて人間的な判断プロセスだ。
また、整備作業の多くは、狭いエンジンルームや車体下部での複雑な手作業だ。ロボット技術が発達しても、自動車という多種多様で複雑な構造物に対する整備作業を完全自動化するのは技術的に困難だ。特に、予期しない錆や腐食、過去の修理履歴による構造変更など、個体差の大きい中古車の整備では人間の柔軟な対応が不可欠だ。
ADAS(先進運転支援システム)の普及により、新たな整備需要も生まれている。衝突被害軽減ブレーキのセンサー校正、レーンキープアシストのカメラ調整、アダプティブクルーズコントロールのレーダー設定など、高精度な調整作業が必要だ。これらの作業には、システムの動作原理を理解し、専用機器を操作し、微細な調整を行う技能が必要で、単純にAIで代替できるものではない。
むしろAI技術は、整備士の作業を支援する強力なツールとして活用されている。故障診断支援システム、部品検索システム、作業手順ガイダンスシステムなど、AIを活用したツールにより整備効率は大幅に向上している。重要なのは、AIに仕事を奪われることを恐れるのではなく、AIを使いこなす整備士になることだ。
また、自動運転車の普及により、従来とは異なる整備需要が生まれる。自動運転システムの定期点検、ソフトウェア更新、センサー清掃・校正、地図データ更新など、新たな業務領域が拡大している。これらはすべて、高度な専門知識を持つ整備士でなければ対応できない業務だ。
お客様とのコミュニケーションも、AIでは代替困難な領域だ。車の不具合の聞き取り、修理方法の説明、費用の相談、予防整備の提案など、人と人との信頼関係に基づくコミュニケーションは、整備士の重要な職務だ。
待遇改善の兆し:自動車整備士の年収アップ戦略
整備士の待遇改善について、ようやく明るい兆しが見えてきた。2025年6月、自動車整備士の業界団体と損害保険大手が約30年ぶりに工賃の基準となる単価の引き上げに合意したのだ。これは業界にとって歴史的な前進だ。
現在の自動車整備士の平均年収は約426万円とされているが、これは他の技術職と比較して決して高い水準ではない。しかし、人材不足の深刻化により、ようやく労働市場の需給バランスが整備士に有利に働き始めている。
実際に、待遇改善の動きは具体的な形で現れている。年間休日120日以上の整備工場が増加し、「整備士が休めない」という従来のイメージは過去のものになりつつある。大手ディーラーから始まった働き方改革が、中小の整備工場にも波及している。
給与面でも改善傾向が顕著だ。特に1級整備士や特殊整備士の資格を持つ整備士に対する評価は急上昇している。俺が知る範囲でも、1級整備士資格を取得後に年収が50万円以上アップしたケースが複数ある。
地域差はあるものの、都市部では整備士の初任給が大幅に改善されている。新卒の整備士で月給25万円以上、経験者では月給30万円以上を提示する求人も珍しくなくなった。これは5年前と比較すると、明らかな改善だ。
また、整備士不足により転職市場も売り手市場になっている。経験豊富な整備士であれば、転職により年収アップを実現するのは決して困難ではない。特に、電動車整備や先進安全装備の整備ができる整備士は、引く手あまたの状態だ。
独立開業という選択肢も魅力的だ。人材不足により、腕の良い整備士が独立すれば、すぐに顧客を獲得できる環境にある。俺が将来的に自分の整備工場を立ち上げようと考えているのも、このような市場環境があるからだ。
さらに、整備士資格の価値向上により、異業種からの転職者も増えている。IT系企業から転職して整備士になるケースや、製造業から転職するケースなど、多様なバックグラウンドを持つ人材が整備業界に参入している。これは業界全体の活性化につながっている。
地域の整備工場が生き残る方法:個人事業主の視点から
大手ディーラーに対して、地域の整備工場がどう生き残るか。これは俺が将来の独立を考える上で最も重要な課題だ。16年の現場経験とマーケッターとしての視点から、生き残り戦略を考えてみたい。
まず重要なのは、大手ディーラーとの差別化だ。ディーラーは特定メーカーの車種に特化しているが、地域の整備工場は全メーカー対応が可能だ。この汎用性は大きな強みになる。特に、複数メーカーの車を所有する事業者や、中古車を多く扱う顧客にとって、ワンストップで整備対応できる工場の価値は高い。
次に、特殊整備分野への特化だ。例えば、電動車専門整備、輸入車専門整備、商用車専門整備、旧車・クラシックカー専門整備など、ニッチな分野に特化することで独自性を確立できる。俺が検討しているのは、電動車と先進安全装備に特化した整備工場だ。この分野はまだ競合が少なく、高い技術力があれば十分に差別化できる。
地域密着型サービスの重要性も見逃せない。ディーラーでは対応が難しい細かな要望や、緊急時の対応、長期間の付き合いによる信頼関係など、地域工場ならではの強みがある。お客様一人ひとりと長期的な関係を築くことで、安定した顧客基盤を構築できる。
また、新たなサービス領域への展開も重要だ。車検・点検に加えて、タイヤ交換・保管サービス、カーコーティング、カーエアコンクリーニング、ドライブレコーダー取り付け、ETC取り付けなど、関連サービスを拡充することで収益の多角化が図れる。
デジタル化への対応も生き残りには不可欠だ。オンライン予約システム、作業進捗の可視化、デジタル点検記録簿など、顧客の利便性向上とともに業務効率化を実現できる。俺のマーケッティング経験も、この分野で活かせるはずだ。
人材確保・育成も重要な要素だ。地域工場の多くが人手不足に悩んでいるが、逆に言えば、良い待遇と働きやすい環境を提供できれば、優秀な人材を確保できる可能性がある。特に、技術向上への投資や資格取得支援を充実させることで、従業員のモチベーション向上と技術力向上を同時に実現できる。
自動車整備士資格の取得戦略:効率的なキャリアパス設計
これから整備士を目指す人、そして現在整備士として働いている人に向けて、効率的な資格取得戦略を提案したい。俺自身の16年の経験と、2026年の制度改正を踏まえた戦略だ。
まず、3級から始める場合の最短ルートだが、制度改正により実務経験が6ヶ月に短縮されるため、高校卒業後なら最短で18歳後半に3級を取得できる。その後2年の実務経験で2級取得が可能になるため、20歳後半には2級整備士になれる計算だ。
しかし、より確実で効率的なのは専門学校ルートだ。2年制の専門学校を卒業すれば、2級整備士の実技試験が免除され、学科試験のみで資格取得できる。実務経験も不要なため、20歳で2級整備士資格を取得できる。
俺の経験から言えば、専門学校での学習は単なる資格取得以上の価値がある。体系的な知識の習得、最新設備での実習経験、同期とのネットワーク構築など、現場に出てから大いに役立つ。特に、2026年から2級に電子制御装置の知識が必要になることを考えると、専門学校での学習はより重要になる。
1級整備士を目指す場合は、さらに戦略的な計画が必要だ。2級取得後、3年の実務経験を積んで1級の受験資格を得る。または、専門学校の1級コース(4年制)を卒業すれば、実技試験免除で1級を取得できる。
1級整備士の価値は今後急激に高まる。2030年からの自動運転車検査員要件強化により、1級整備士の希少価値は確実に上昇する。年収面でも、他の資格レベルとの差は拡大していくはずだ。
特殊整備士資格の選択も重要だ。自動車電気・電子制御装置整備士は、電動車時代において特に価値が高い。自動車車体・電子制御装置整備士は、事故車修理や改造車検査など、専門性の高い業務に従事できる。自動車タイヤ整備士は、タイヤ専門店での勤務や独立開業に有利だ。
資格取得と並行して重要なのが、実務経験の質だ。単に年数を重ねるのではなく、多様な車種・故障事例を経験し、新技術に積極的に触れることが重要だ。特に、電動車整備、先進安全装備の整備、輸入車整備など、付加価値の高い業務経験を積むことで、将来のキャリアアップにつながる。
継続的な学習も欠かせない。技術の進歩が早い自動車業界では、資格取得後も常に新しい知識・技術を習得し続ける必要がある。メーカー研修、業界団体の研修、専門誌の購読、技術セミナーへの参加など、多様な学習機会を活用すべきだ。
整備工場経営者が知っておくべき法改正ポイント
2026年7月に公布され、一部は既に施行されている自動車整備事業の規制見直しについて、現場で働く整備士の視点から重要なポイントを解説したい。
最も影響が大きいのが、認証工場の機器要件見直しだ。整備用スキャンツールの設置が必須となり、一方でタイヤの傾きを測定する機器などは不要になった。これは現場の実態に合わせた非常に合理的な変更だ。
俺の経験からも、スキャンツールなしに現代の自動車整備は不可能だ。エンジン制御、トランスミッション制御、ブレーキ制御、エアコン制御など、あらゆるシステムが電子制御化されており、故障診断にはスキャンツールが必須だ。これが法的に義務化されることで、整備の品質向上が期待できる。
一方、使われなくなった機器の設置義務が廃止されることで、認証取得のハードルが下がる。これは新規参入を促進し、業界の活性化につながるはずだ。
指定工場(大型)の最低工員数が5人から4人に緩和されたことも重要だ。ただし、省力化設備の導入、合理的な管理体制の確保、工員の処遇確保、工員の質の確保という条件がある。これは単純な人員削減ではなく、効率化と品質確保を両立させる趣旨だ。
オンライン研修・講習の解禁も画期的だ。整備主任者研修や自動車検査員研修の座学部分がオンラインで受講可能になった。これにより、地方の整備工場でも研修受講がしやすくなり、人材育成の機会が拡大する。
スキャンツール等による点検可能範囲の拡大により、作業効率の大幅な改善が期待できる。従来はノギスで測定していたブレーキと床面のすき間がスキャンツールで確認できるようになり、1台あたり平均3分15秒の時間短縮が可能になった。
これらの法改正は、整備業界の近代化と効率化を促進する内容だ。特に中小の整備工場にとっては、設備投資の効率化、人材確保の容易化、業務効率の向上など、多くのメリットがある。
ただし、法改正に対応するためには、設備投資や従業員教育が必要だ。特にスキャンツールの導入は、機器購入費用だけでなく、操作技術の習得、定期的なソフトウェア更新など、継続的なコストが発生する。これらを含めた事業計画の見直しが必要だ。
俺が予想する自動車整備士の未来像:2030年代のシナリオ
16年の現場経験とマーケッターとしての市場分析を基に、2030年代の自動車整備士の姿を予想してみたい。これは決して希望的観測ではなく、現在の技術動向と制度改正の方向性から導き出されるリアルなシナリオだ。
2030年代前半には、電動車の普及率が50%を超えるはずだ。これに伴い、整備士の主要業務は電子制御システムの診断・調整に移行する。従来の機械的な整備作業は減少し、代わりにソフトウェア更新、センサー校正、システム設定変更などの業務が中心になる。
この変化により、整備士の職務はより技術的、専門的になる。単純作業は減少し、高度な判断力と専門知識が求められる業務が増加する。結果として、整備士一人当たりの付加価値は大幅に向上し、これが待遇改善につながる。
自動運転車の普及により、新たな整備需要も生まれる。自動運転システムの定期メンテナンス、センサークリーニング、地図データ更新、ソフトウェアアップデートなど、従来にない業務が日常化する。これらの業務は高い専門性を要求し、整備士の価値をさらに高める。
人材不足問題については、2026年の制度改正と待遇改善により、徐々に解決に向かうと予想する。実務経験短縮により資格取得のハードルが下がり、給与水準の向上により業界の魅力が高まる。また、異業種からの転職者増加により、多様な人材が整備業界に参入する。
整備工場の形態も大きく変化する。従来の修理中心の工場から、予防保全、システム更新、カスタマイズなどのサービスを提供する「自動車技術サービスセンター」へと進化する。物理的な修理作業は減少し、代わりにデータ解析、システム最適化、技術コンサルティングなどの高付加価値サービスが中心になる。
地域格差も縮小する。オンライン診断、遠隔サポート、デジタル技術資料などにより、地方の整備工場でも最新技術に対応できるようになる。これにより、大都市圏に集中していた高度な整備サービスが全国に普及する。
独立開業の機会も拡大する。高度な専門性を持つ整備士であれば、特定分野に特化した専門工場として成功する可能性が高い。俺が計画している電動車・先進安全装備専門の整備工場も、このような時代背景があってこそ実現可能だ。
労働環境も大幅に改善される。デジタル化により事務作業が効率化され、予防保全の普及により緊急対応が減少し、働き方改革が進む。結果として、整備士という職業の社会的地位と魅力が大幅に向上する。
これから自動車整備士を目指す人へのメッセージ
この記事を通じて伝えたかったのは、自動車整備士という職業の将来性への確信だ。16年間現場で働き、業界の変化を肌で感じてきた俺だからこそ言えることがある。
確かに整備士を取り巻く環境は厳しい。人材不足、技術の高度化、待遇の問題など、課題は山積している。しかし、これらの課題こそが、整備士の価値向上につながる要因でもある。
2027年の制度改正は、まさに転換点だ。資格体系の合理化、受験要件の緩和、実務に即した内容への変更により、整備士資格はより取得しやすく、より価値のあるものになる。特に1級整備士の価値は、自動運転車検査員要件の強化により飛躍的に高まる。
電動車の普及、AI技術の発達、自動運転技術の実用化など、技術革新は整備士の仕事を奪うのではなく、より高度で専門的な職業に押し上げる。単純作業はAIやロボットが担い、整備士は判断力と専門性が求められる業務に集中できるようになる。
待遇改善の兆しも確実に見えている。人材不足により労働市場が売り手市場に転じ、給与水準の向上、労働環境の改善が進んでいる。この流れは今後さらに加速するはずだ。
俺自身、マーケッターとして働きながらも、車への愛情は変わらず、将来的には自分の整備工場を立ち上げる予定だ。検査員資格の取得も検討している。それは、整備士という職業の将来性を確信しているからだ。
これから整備士を目指す人には、ぜひ専門学校での体系的な学習をお勧めしたい。特に電子制御技術、電動車整備技術は必須の知識となる。資格は1級まで取得することで、将来の選択肢が大幅に広がる。
現在整備士として働いている人には、継続的な技術習得と資格のアップグレードをお勧めしたい。変化を恐れるのではなく、変化をチャンスと捉えて行動することが重要だ。
自動車は今後も社会に不可欠なインフラであり続ける。その安全と性能を支える整備士の役割は、技術が進歩すればするほど重要になる。AI時代だからこそ、人間にしかできない判断力と専門性を持つ整備士の価値は高まるのだ。
整備士という職業に誇りを持ち、技術向上に努め、変化を恐れずに前進する。そんな整備士が活躍する時代が、すぐそこまで来ている。