自動車整備士の資格|全種類と難易度、最短合格ロードマップを徹底解説
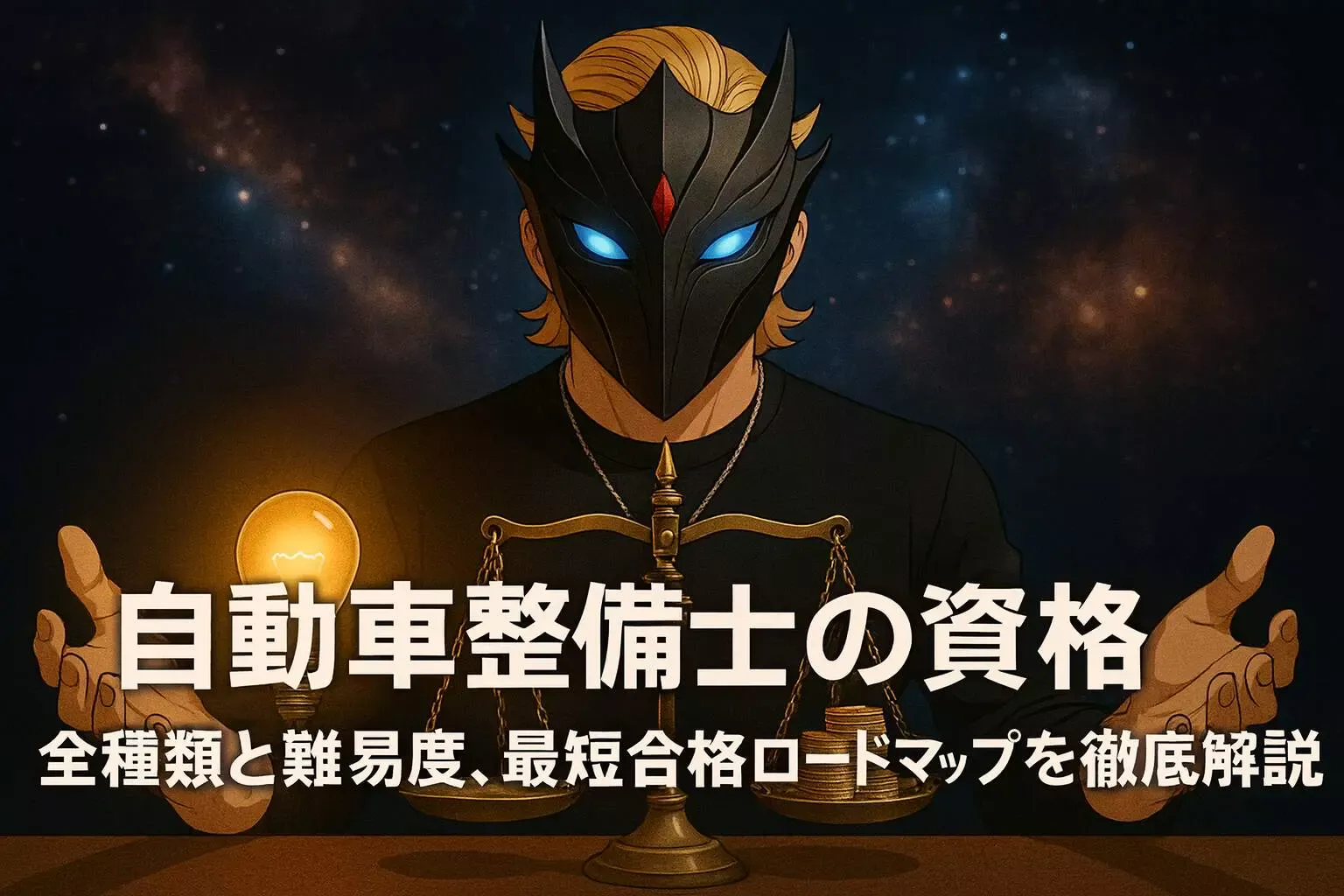
「自動車整備士になりたいけれど、資格の種類が多くてどれを目指せば良いか分からない」 「3級の難易度はどれくらい?俺でも合格できるか?」 「働きながらでも資格は取れる?一番効率的な取り方が知りたい」
俺は中学生の頃にハマったイニシャルDの影響でレーサーやF1の整備士を目指そうと思い、高校生の頃に通信教育で整備士3級の取得を目指した。そして、最終的に俺は整備士歴16年で国家資格である小型自動車一級整備士資格を持っている。
経歴はこちらを参照してくれ。俺のプロフィールと経歴
自動車整備士という仕事に興味を持ったキミが、まず最初に考えるのが「資格」だろう。
自動車整備士の資格は、国が定める国家資格であり、その種類は業務内容に応じて細かく分かれている。どの資格を取得するかによって、できる仕事の範囲やキャリアパス、さらには将来の年収も大きく変わってくるため、最初の情報収集が非常に大切だ。
しかし、インターネット上には断片的な情報も多く、全体像を体系的に理解するのは簡単じゃない。俺が高校生の時はまだパソコンでの情報収集が主となっていたが、今はあらゆる人が簡単に情報を発信している。
そこでこの記事では、自動車整備士の資格に関するあらゆる情報を1ページに凝縮。この記事を読めば、以下のことが分かるように書いた。
- 自動車整備士の国家資格の全種類とその役割
- 3級から1級までのリアルな難易度(合格率データ付き)
- あなたに合った資格の取り方が見つかる4つのロードマップ
- 資格取得後のキャリアと将来性
- 2025年の資格制度の改革によって変わる整備業界の未来
トヨタ名古屋自動車大学校を卒業後、愛知トヨタ~ランボルギーニまで経験し整備士歴16年の俺が、専門用語をなるべく避けつつ、図解を多用してどこよりも分かりやすく解説。
この記事を読み終える頃には、キミが今何をすべきか、どの資格を目指すべきかが明確になっているはずだ。夢への第一歩を、俺は後押ししたい。

とはいえ、極論を言えば、自動車整備士の資格を持っていなくても、整備をやってはいけないということはない。その理由もあとで解説しよう。
自動車整備士の資格の種類と体系が一目でわかる全体像
この記事で解説する自動車整備士資格の全体像を最初に示そうと思う。自動車整備士の資格は、大きく分けて「1級」「2級」「3級」の等級と、専門分野に特化した「特殊整備士」の4つに分類される。まずはこの関係性を掴んでから、詳細を読み進めてほしい。
【図解:自動車整備士の国家資格体系図】
- 頂点に「1級」、その下に「2級」、基礎となる「3級」をピラミッド形式で配置。
- ピラミッドの横に、独立した形で「特殊整備士(車体・電気装置・タイヤ)」を配置。
- 各級から矢印を引き、「できる業務の範囲(例:3級は基本的な整備、2級は分解整備全般、1級は指導・高度診断)」を簡潔に記載する。
自動車整備士の資格【全種類】を徹底解説!仕事内容はどう違う?
自動車整備士の国家資格は、それぞれに役割と業務範囲が定められている。ここでは、各資格がどのような仕事に対応しているのか、具体的に解説していく。キミが将来どんな整備士になりたいかを想像しながら読み進めてみてくれ。
以下の内容について話していく。
- 一級自動車整備士とは?(最上級資格としての位置付け)
- 二級との決定的な違い(高度な診断能力、指導的役割)
- 一級を持つことで開けるキャリアパス(工場長、教育者、メーカー勤務など)
- 取得のメリット:年収への影響と転職市場での圧倒的な価値
- 一級の種類:小型、大型、二輪の違い
自動車整備士の頂点「一級自動車整備士」
世間が一般的に国家一級整備士というのはこの資格だ。一応現段階では自動車整備士資格の中では最高クラスとなっている。正式には一級小型自動車整備士だ。
だが、今後は自動車検査員が最もレベルの高い資格になる見通しだ。
その理由は2027年に予定されている自動車検査員の資格取得要件が一級自動車整備士資格を持った者というのが条件になるから。自動車整備士の資格制度や法改正についてはこちらで書いている。
とはいえ、2025年10月における現段階では最も格上の整備士資格だ。
一級自動車整備士の種類は3つ
ちなみに一般的に俺らが言う国家一級と言えば、乗用車などを対象とした「小型自動車」の資格を指す。じゃあ、他に何があるか?
一級大型自動車整備士
面白いことにこの資格はゴーストスキル。と俺は読んでいる(笑)
なぜなら、この資格、国交省には記載があるものの、2025年10月現在に至るまで、一度も国家試験が実施されていないからだ。理由に関しては二級自動車整備士との差別化が難しいという話が出されているが・・・
確かに実務では大型と小型分けたところで大差はない。むしろ俺は国家二級のディーゼルとガソリンの違いの方が大切だと思っている。やはり、ディーゼルも電子化が進んできたとは言え、働く車が多い日本では機械式のディーゼル車まだまだ多い。
特にトラックを多く扱う工場の場合それは顕著に現れるし、未だにメカニカルガバナを使っている車種も入庫してくる。
今のディーゼルの国家資格でガバナについて触れているかは不明だが、触れていても内容も少ないだろう。
一級二輪自動車整備士
こちらも同様にゴーストな資格だな。そもそも自動車整備士資格を持っていれば、二輪車の燃焼機関に関しても触れるため、差別化が難しいのが現状だろう。
俺が高校生の頃は二輪自動車整備士の取得学校があったが、今は国家試験すら実施していない状況だ。
しかし、二輪自動車に特化した整備士資格はあってもいいと俺は思っている。というのも、基本構造は同じだが、自動車整備士としてしか実務をこなしていなかった者が、いきなり二輪自動車を整備しろと言っても、意外と出来ないことが多い。
もちろん、修理書を見れば誰でも出来るが、まず、自動車のように部品を簡単には外せない。カウルがついているものやスクーター系になると特にやっかいだ。
今まで車しか触ってきませんでしたという人に取って、異業種としてバイクの整備士になった時にまず頭を悩ませるだろう。趣味でバイクも触っている人間ならまだしも、やはり、需要は少ないとは言え、バイクの専門学校と二輪車専用の資格はあってもいいんじゃないかと思っている。
未だにバイクの世界はキャブレターが多いからな。今の自動車整備士はキャブレターを触れないし、専門学校でもキャブレターを教えなくなったくらいだ。
俺が通っていたトヨタ名古屋自動車大学校では、俺の代でキャブレターの講義は無くなり、俺の弟は学年が一つ下だが、キャブ車は触らなかったと言っていた。
俺は3Sエンジンで学び、弟は4Aエンジンで学んだからな。
一級小型自動車整備士と二級自動車整備士の違い
ハッキリ言う。
これは診断能力の違いだ。正直それ以外にないと思っている。
診断に関しては絶対に一級の資格を有するというより、国家一級の考え方と能力が重要になってくる。二級自動車整備士では、診断の流れを簡単には説明するが、高度診断スキルの内容までは触れない。
今や電子化が進み、レーンキーピングや様々なアシスト機能に対して故障が発生する中で、実務経験上、二級レベルだとなかなか診断が難しい。
まあ、OJTがしっかりしているディーラーであれば、国家に級であっても同様のスキルは有しているが、町工場やチャネルの違うディーラーでは能力が大きく異なってくる。
愛知トヨタをひいきする訳では無いが、俺がこの会社にいた頃は国家一級の取得率は100%だった。その分、軍隊みたいな研修制度だったがな。俺の愛知トヨタ時代の話は別の記事で書いているから興味あれば見てくれ。
後輩を指導するスキル
もう一つ国家一級の自動車整備士は後輩を指導するための論理的な教え方ができるというのがポイントだと思っている。二級自動車整備士時代には体感や感覚ベースでは理解できていても、教える時に言葉に出来ないということがあるだろ?
どちらかと言うと俺がそのタイプなのだが、正直、論理的に教えるのは苦手だ。
後輩のタイプに合わせてステップバイステップで教えるのが得意な俺の場合、一級小型自動車整備士を取得するというか、試験を受けるために勉強をし始めてようやく、言葉として説明することが出来るようになった。
実務ではなんとなく出来ているし、自分の中では理解出来ていても、相手に教えるとなると言葉に出来ないことってあるだろ?
その感覚だ。
一級小型自動車整備士のメリットや年収への影響
正直に言ってない。
むしろこの記事を書いている2025年10月現在では、自動車検査員の方が重宝されるし、手当も良い。
俺が求人を探している時にも、一級小型自動車整備士と自動車検査員の資格手当はほとんどの場合、検査員の方が上だった。
例えば、一級自動車整備士の場合・・・
3000円、1万円、2万円、3万円を見かけた。
自動車検査員の場合・・・
1.5万円、3万円、5万円というのを目にした。
つまり、現段階では自動車検査員の方が2026年に向けた将来的にも重宝されるというか、むしろ供給が少なくて、基本給も上がってくるのではないかと思っている。
整備士のスタンダード「二級自動車整備士」
やはり自動車整備士と言えば、二級だ。これは就職活動や転職活動の時にもほぼ必須となってくる。が、最近ではそうでもない現状がある。
その理由が整備士人口の減少だ。
もちろん、大手やディーラーでは二級自動車整備士を持っていないといけないが、町工場では3級自動車整備士でもOKだったり、そもそも整備士資格を必要としていない場合も多々見られるようになった。
これはdodaなどに掲載されている求人票を見ても明らかだ。
とはいえ、まだまだ二級自動車整備士の資格は最もスタンダードだし、2026年以降はステップアップの土台としてますます重要な位置づけになってくるだろうから、必ず取るようにしたい。
以下について解説していく。
- なぜ二級が「実質的なスタートライン」と言われるのか?
- 二級で可能になる「分解整備」とは何か(エンジンやブレーキなど重要保安部品の整備)
- 二級資格の4つの種類と専門性
- 二級ガソリン自動車整備士:最もポピュラーな資格
- 二級ジーゼル自動車整備士:トラックやバスのプロフェッショナル
- 二級自動車シャシ整備士:基本的に足回り専門
- 二級2輪自動車整備士:バイク整備の専門家
二級自動車整備士がスタートラインと言われる理由
これは簡単に言えば、分解整備ができるかどうかが鍵となってくる。また、自動車整備主任者になるためには二級自動車整備士以上を有していないといけない。
つまり、二級自動車整備士の資格を持っていないとまともにお客さんの車を触らせることが出来ないということだ。
じゃあ、三級自動車整備士は意味のない資格なのか?
まあ、正直に言えば俺は意味のない資格だと思ってはいる。が、それは車がもともと好きで、それなりに部品の名前を知っていたりする場合だ。
全く無知の状態からなのであれば、三級自動車整備士の資格を取るために勉強することは、部品名称や、車の構造を理解するうえでは必須となってくる。
基本的な概念を知らないまま、国家二級自動車整備士の資格を取ることは困難だ。
では分解整備とはなんなのか?
分解整備というのは簡単に言うと、命に大きく関わってくる重要な部品の整備をすることだ。例えば、ブレーキ。
ブレーキには様々な部品が使われていて、ブレーキパッド、ブレーキキャリパー、ピストン、スライドピン、ブーツ、ブッシュ…など。ブレーキと一言に言っても色々な細かい部品で1つの構成になっている。
ここで、【ブレーキキャリパーを外す作業】を行う場合、分解整備となり、二級自動車整備士の資格が必要となってくる。ブレーキキャリパーを外さない場合のブレーキパッド交換は分解整備にならない。
もっと詳しく言うと、仮にブレーキパッドが整備士のミスで不具合が発生したとしても、なんとかピストンがブレーキディスクにあたり、完全に飛び出してブレーキが全く効かないということにはならないからだ。
もちろん、そのまま走行してピストンを削ってしまえば、抜け落ちてしまうのだが・・・
過去にパッド交換をケチってピストンを削って走っていたお客さんがいたが、ピストンが擦れて短くなり、ピストン自体がキャリパーから脱落していた。
ここで、考えてみてほしい。キャリパーがしっかりついていれば、ピストンはなんとかブレーキとしてディスクローターに当たり、制動力としては弱すぎるものの、一応ブレーキを書けることは出来る。
もし、キャリパーがなんらかのミスで外れた場合はブレーキをかけることが出来ない。
=減速できない=追突する
という結果を招く。だから分解整備をするには、二級以上の自動車整備士資格が必要なんだ。
二級自動車整備士の4つの種類
さて、俺は二級自動車整備士のガソリンとディーゼルを保有している。トヨタ名古屋自動車大学校にて2年間の普通整備科(現在の名称は自動車整備科2年課程だ)を経て、愛知トヨタ自動車に入社前に試験を受け合格。
ガソリンとディーゼルは両方取得する必要はなく、どちらかを持っていれば、整備主任者などになれる。
二級ガソリン自動車整備士
もっともポピュラーで今走っている車の基準はガソリンよりだ。最近ではディーゼル傾向もあるが、どうしてもディーゼルは海外勢に負ける。BMWやメルセデスなどはディーゼルに強いからな。
今後環境を考えるとガソリンはなくなっていくだろうが、まだまだガソリン車の時代は続いていくと思っている。ガソリン車のエンジンの燃焼はスパークプラグによる点火だ。ガスコンロと同じイメージだ。
ガスコンロもガスが出ていて、その部分にスパークを飛ばすことで火がつくようになっている。ガスコンロもスパークプラグと同じように「がいし」があり、上に向かって突き出ているはずだ。
その他の部品に関しては共通の物が多いため、大きな違いと言えば、エンジン、つまり燃焼機関の違いとそのあたりに関する知識。一般的に自動車整備士二級を持っていると言えば、ガソリンの方の資格を指す場合が多い。
二級ジーゼル自動車整備士
こちらはガソリンと違って自然に着火することで燃焼する。学生時代は「着火と点火」は一緒だろと思っていたが、しっかりと構造を理解すれば意識も変わる。ディーゼル車の場合は、混合気を圧縮していき、温度が上がっていくと火が出る仕組みだ。
例え話をだすと、自転車の空気入れ。自転車の空気を入れていると筒が熱くなるだろ?
あれを繰り返していくと温度が上昇していくんだ。
エネオスのエネゴリくんだったか忘れたが、空気でお湯を沸かすっていうのはその原理を使っているからなんだ。空気を圧縮することで温度は上がっていくからディーゼルは考え方は単純。
だが、部品名称が多すぎて、当時は嫌気がさした記憶がある。今後はメカニカルではなく、電子的なディーゼルの内容に変わっていくだろう。
二級2輪自動車整備士
2輪は漢数字じゃないのが前々から気になっていたが、こちらは現在も試験が行われている。ようはバイクを触るための入門みたいなもんだと思っている。一応、三級2輪も試験は行われている。
俺はバイクしか触らん!っていうのなら、断然こちらのほうが問題は簡単だし、内容も薄いから、バイクで良ければこちらを取れば良い。学費なども自動車と比べてかなり安いからな。
二級自動車シャシ整備士
二級自動車シャシに関しては二級自動車ガソリン・ディーゼルを取得する課程で理解できるので、俺には取得する意義を見いだせないが、存在する。
整備振興会に一級の講習を受けにいったときに、二級自動車シャシを受けている人はそこそこ存在したが、こちらに関しては俺はわからない。
ちなみに、指定整備は不可。ただし原動機を除く「分解整備」なら可能だ。
最低限の知識を得るためになのか、一応触れるようにするためなのか・・・
いずれにせよ、そのうち無くなると俺は思ってる資格だ。
理由は令和二年の時のデータになるが、国交省が発表している受験者6名に対して合格したのが2人。しかも全国で集計したものだ。日本国内でたった6名しか年間で受験しない資格はそのうち無くなる。
すべての基礎となる「三級自動車整備士」
まず、前提として『全くの無知の状態』である場合、すべての基礎となるのは三級自動車整備士だ。専門学校でも二級を取得するために、三級は取得はしないが勉強はする。
実際俺がトヨタ名古屋自動車大学校に通っていた時は、1年生の時に三級自動車整備士の内容を勉強したし、シャシも勉強した。しかし、最終的な目標は二級自動車整備士のため、あえて三級は取得しない。
大手やディーラーでは三級自動車整備士以下は募集条件に入っておらず、入社するためには二級自動車整備士の資格が必要となってくる。
これは先程もいった分解整備や整備主任者、今後の一級取得からの検査員という流れがあるからだ。
つまり、スキルとしての意味はなく、“自動車に関する最低限の知識を持っているという証”のようなものだ。
高校生や未経験キャリアからの三級取得の意義
これはおおいにあるだろう。
というのも、例えば高校生が自動車整備専門学校に行きたいとなった場合、三級自動車整備士の資格を持った状態だと、学校から推薦をもらえることもあるし、入試の段階で、本気度が見込まれて優遇されるケースがある。
もちろん、学校からしたら三級取得は意味はないが、学生を見る視点であれば、将来整備士になりたいという状況がわかる。
また、未経験の状態から整備士になりたい場合、いきなり学校も行かずに二級自動車整備士を取得するのはハードルが高い。三級自動車整備士があれば、大手やディーラーには行けなくても、民間整備工場は雇ってくれるところが多い。
探せば未経験OKや三級からOKというのはよく見る。
自動車のことを全く知らないのなら三級自動車整備士は取っておいてもいいだろう。
特定分野だけOKな「特殊整備士」
これが少し面白いんだが、特殊整備士というのがある。正直、これも何がしたいのだか、国交省の考えることが不明だ。
詳しくは自動車整備士資格制度等の見直しについての報告書に記載がある。
お国の言葉で書かれているから読みにくいのだが、簡単に以下の内容について話していく。
- 特殊整備士とは?特定の分野を極めるための資格
- 3つの専門分野
- 自動車タイヤ整備士:タイヤに関するすべての作業
- 自動車電気装置整備士:電装系のスペシャリスト(今後の需要増かも)
- 自動車車体整備士:板金・塗装のエキスパート
自動車タイヤ整備士
タイヤの整備を行うためのタイヤ整備士だが、一級または二級を有するものからの指示があり、電子制御装置の作業を伴わないため、電子制御に関わる知識や技能は持っていなくてもいい。
自動車電気装置整備士
こちらは特定の条件が揃っており、かつ整備主任者講習を受ければ整備主任者になることができる。電子制御装置に関わる特定整備ができる資格だ。
自動車車体整備士
こちらも特定の条件+整備主任者の講習を受けることで主任者になれる。
資格名が分かりづらいのだが、ボディーやフレームの専門的な立ち位置の資格となる。板金などに必要な知識が得られる。俺の経験上、一つ気になることがあるからここで言いたいが、板金をやっている人はよく、「板金」じゃなくて「鈑金」と言ってくる。
ハッキリ言うが、常用漢字ではないから俺は「鈑金」とは書かない。
こだわりが強いのはいいが、人に強要するのはどうかと思う。特に40代からが多かったな。
30代からはそんなことはどうでもいいという考えだ。検索でも「板金」とほとんどの人が打つ。話が逸れたが、どうしても伝えたかった。
自動車整備士の資格【難易度】を合格率と勉強時間から徹底比較
「自分に合格できるだろうか?」という不安を解消するため、ここでは各資格の難易度を客観的なデータと具体的な学習内容から分析する。特に将来整備士を目指す人や未経験から転職しようとする方が気になる「整備士3級の難易度」については、重点的に解説していく。
令和6年第一回と第二回で実施された学科と実技合格率は以下の通り。
令和6年度第1回自動車整備技能登録試験「学科試験」の試験結果
R06.10.06実施( )内前年同期実績
出典は日本自動車整備振興会連合会だ
| 種 類 | 申請者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% | 受験率% |
| 二級ガソリン | 2,425 (2,519) | 2,310 (2,433) | 1,383 (1,492) | 59.9 (61.3) | 95.3 (96.6) |
| 二級ジーゼル | 385 (424) | 370 (405) | 185 (230) | 50.0 (56.8) | 96.1 (95.5) |
| 二級2輪 | 640 (759) | 617 (733) | 494 (572) | 80.1 (78.0) | 96.4 (96.6) |
| 三級シャシ | 851 (966) | 819 (942) | 540 (607) | 65.9 (64.4) | 96.2 (97.5) |
| 三級ガソリン | 3,863 (3,857) | 3,756 (3,756) | 2,799 (2,779) | 74.5 (74.0) | 97.2 (97.4) |
| 三級ジーゼル | 286 (358) | 269 (343) | 166 (198) | 61.7 (57.7) | 94.1 (95.8) |
| 車 体 | 302 (341) | 293 (334) | 235 (267) | 80.2 (79.9) | 97.0 (97.9) |
| 合 計 | 8,752 (9,224) | 8,434 (8,946) | 5,802 (6,145) | 68.8 (68.7) | 96.4 (97.0) |
令和6年度第1回自動車整備技能登録試験「実技試験」の試験結果
R07.01.19実施( )内同一種類の前回成績
| 試験種目 | 申請者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% | 受験率% |
| 二級ガソリン自動車 | 50 (51) | 49 (48) | 20 (20) | 40.8 (41.7) | 98.0 (94.1) |
| 三級自動車シャシ | 60 (46) | 55 (43) | 46 (21) | 83.6 (48.8) | 91.7 (93.5) |
| 合 計 | 110 (97) | 104 (91) | 66 (41) | 63.5 (45.1) | 94.5 (93.8) |
令和6年度第2回自動車整備技能登録試験「学科試験」の試験結果
R7.03.23実施
( )内前年同期実績
| 種 類 | 申請者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% | 受験率% |
| 一級小型(筆記) | 2,982 (2,865) | 2,895 (2,784) | 1,902 (1,645) | 65.7 (59.1) | 98.4 (98.2) |
| 二級ガソリン | 9,423 (9,729) | 9,287 (9,600) | 8,001 (8,331) | 86.2 (86.8) | 98.6 (98.7) |
| 二級ジーゼル | 6,950 (7,583) | 6,864 (7,515) | 6,471 (7,017) | 94.3 (93.4) | 98.8 (99.1) |
| 二級シャシ | 194 (351) | 192 (321) | 182 (276) | 94.8 (86.0) | 99.0 (91.5) |
| 三級シャシ | 1,645 (1,892) | 1,588 (1,816) | 1,070 (1,224) | 67.4 (67.4) | 96.5 (96.0) |
| 三級ガソリン | 3,838 (3,823) | 3,682 (3,659) | 2,519 (2,399) | 68.4 (65.6) | 95.9 (95.7) |
| 三級ジーゼル | 665 (712) | 637 (688) | 376 (396) | 59.0 (57.6) | 95.8 (96.6) |
| 三級2輪 | 244 (278) | 236 (265) | 207 (220) | 87.7 (83.0) | 96.7 (95.3) |
| 電気装置 | 136 (197) | 135 (192) | 106 (158) | 78.5 (82.3) | 99.3 (97.5) |
| 車 体 | 675 (604) | 668 (599) | 626 (554) | 93.7 (92.5) | 99.0 (99.2) |
| 合 計 | 26,752 (28,034) | 26,184 (27,439) | 21,460 (22,220) | 82.0 (81.0) | 98.0 (98.0) |
令和6年度第2回自動車整備技能登録試験「一級小型自動車学科試験」の試験結果
| 一級学科試験申請者数 | 2,982人 |
| 筆記試験申請者数 | 2,941人 |
| 口述試験のみ申請者数 | 41人 |
| 筆記試験日 | 令和7年3月23日 |
| 筆記試験申請者数 | 2,941人 |
| 筆記試験受験者数 | 2,895人 |
| 筆記試験合格者数 | 1,902人 |
| 合 格 率 | 65.7% |
| 口述試験日 | 令和7年5月11日 |
| 筆記試験合格者数 | 1,902人 |
| 口述試験のみ申請者数 | 41人 |
| 口述試験受験予定者数 | 1,943人 |
| 口述試験受験者数 | 1,938人 |
| 一級学科試験合格者数 | 1,910人 |
| 合 格 率 | 98.6% |

学科と実技はいつもずれているから毎回整備振興会のデータはみにくいんだよな。もし、この記事を整備振興会の人が読んでたら直してくれ・・・
「整備士3級の難易度」は低い?合格率は高いが注意すべき点
過去にとらわれる必要はない。正直、直近の整備士試験は一気に問題内容が変わってきた。これは電子制御が増えてきたからで、整備振興会の人間もついに「この問題で合格しても意味ないよね!」と気づいたそうだ。
振興会の人が言ってたから間違いない。
で、だ。
反論を恐れずに言えば、三級自動車整備士なんて簡単すぎるほど簡単だ。イニシャルD好きか?それとも湾岸ミッドナイト?はたまた、よろしくメカドックか。
なんでもいいが、車が好きな人間からしたら、三級自動車整備士なんて簡単に覚えられる。大したことはない。
とは言っても、部品名称などをしっかり把握しておかないと、混乱することもあるので、そこは注意が必要だ。
三級自動車整備士は通信教育で取れる
結論を言えば、取れる。
取れないと言っている人もいるが、それは受験しないと取れないと言っているだけ。そんなの当たり前だろ?
国家資格が受験なしに取れるわけがない。
でだ、三級自動車整備士に必要な条件を以下に示す。これは国交省に記載されているから、間違いない。この記事を書いている現在最も最新の情報だ。
- 無資格の場合、実務経験6ヶ月
- 試験に合格する
たったこれだけ。1年半とか実務経験は必要ない。
実務経験はどこで積む?
もっとも楽に実務経験が詰めるのは『ガソリンスタンド』だ。
俺も高校生の時にガソスタで実務経験を積んだ。というか、ガソスタは在籍さえしていれば、実務をしたかどうかは正直判断できないから、実務経験とみなされる。いや、そう見る以外にないんだ。
仮にガソリンしか入れてない、窓しか拭いていないという場合でも、実務経験として使える。あるいは、無資格OKの民間整備工場だな。(※民間整備工場はブラック企業が多いから注意)
もし、家の近くにガソスタや将来就職したい整備工場があれば、実務経験を積む+将来の給料アップのために長期在籍をしてもいいと思う。
二級自動車整備士の難易度
自動車整備士と言ったら国家二級以上を指す。これは実務経験(ガチで車を触っている経験)が求められるからだ。基本的に求人をしている会社は三級自動車整備の資格を持ってますと言ったところで、鼻で笑われる。
実用的ではないというのが理由だ。そういう風潮もあり、二級自動車整備士以上が、一般的に整備士として認識される。
受験月によって合格率が大幅に異なる理由を分析
改めて出すが、まずは学科と実技のデータは直近のもので以下の通り。
2025/3 学科
| 種 類 | 申請者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% | 受験率% |
| 二級ガソリン | 9,423 (9,729) | 9,287 (9,600) | 8,001 (8,331) | 86.2 (86.8) | 98.6 (98.7) |
| 二級ジーゼル | 6,950 (7,583) | 6,864 (7,515) | 6,471 (7,017) | 94.3 (93.4) | 98.8 (99.1) |
2024/10 学科
| 種 類 | 申請者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% | 受験率% |
| 二級ガソリン | 2,425 (2,519) | 2,310 (2,433) | 1,383 (1,492) | 59.9 (61.3) | 95.3 (96.6) |
| 二級ジーゼル | 385 (424) | 370 (405) | 185 (230) | 50.0 (56.8) | 96.1 (95.5) |
2025/1 実技
| 試験種目 | 申請者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% | 受験率% |
| 二級ガソリン自動車 | 50 (51) | 49 (48) | 20 (20) | 40.8 (41.7) | 98.0 (94.1) |
3月と10月で合格率が大幅に異なる理由
合格率を見ると、3月と10月の学科で大きく数値が異なる。
2025/3の合格率はガソリン86.3%、ディーゼル94.3%だ。
2024/10の合格率はガソリン59.9%、ディーゼル50.0%となっている。
なぜ、こんなにも差が出るのか?
答えは簡単だ。

3月に受験するものは整備士専門学校を出ているからだ。
自動車整備専門学校に通っていれば、学校内で試験に合格してさえいれば、国家試験の実技免除が受けられる。実技免除なので、実際には学科だけ国家試験で合格すればいい。
ほとんどの学校では、就職前の学科試験に向けて、試験対策が行われる。
例えば、俺が通っていたトヨタ名古屋自動車大学校の場合。
俺は頭が良くなく、実技はいつも点数が高かったが、学科はマジでやばかった。電子制御とシャシは特に嫌いで、赤点を取ったことも何度もある。赤点を取ると、追試代(確か1つにつき3500円)を券売機で購入し、学校のテスト用紙に貼っていた記憶がある。
こんなこともあったせいで、俺の成績順位は下から数えたほうが早く、試験対策前にはFクラスという下から二番目のクラスに分けられた。
終電前の23時すぎまで学校に残り、当時の大橋先生に鍛えられた。(まだいるかわからないが、めちゃくちゃ厳しいけど、こっちが本気で取り組んだら本気で答えてくれる先生はこの人だけ。)
もし、トヨタ名古屋自動車大学校に行く人がこの記事を見ていたら、大橋先生にこのブログを見て、きたと言ってくれ。きっと喜ぶはずだ。
逆にこれがあったおかげで、国家試験では、ガソリンもディーゼルも100点で合格したのだが(笑)
つまり、試験対策で鍛えられた学生たちが、3月に挑むため、合格率は劇的にアップする。というのが俺の考えだ。まず間違っていないだろう。
一級自動車整備士の難易度

俺は一回落ちた過去問を結構やったつもりだったが、2問足りなかった。
正直難しい。いや、難しいというより、計算問題が大人の頭になると時間がかかる。残業をしまくっている中、週末しか勉強に使えないし、家族サービスもしないといけない。
こんな時間のない大人が勉強するなんて厳しい話だ。
以下、について話していく。
- 筆記試験の合格率が示す難しさ
- 口述試験という最後の関門:何が問われるのか?
- 求められる知識レベル:整備技術だけでなく、環境保全、安全管理、顧客対応など広範囲
- 合格までに必要な学習期間と、効果的な勉強法
2025/3 直近の筆記試験
| 種 類 | 申請者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率% | 受験率% |
| 一級小型(筆記) | 2,982 (2,865) | 2,895 (2,784) | 1,902 (1,645) | 65.7 (59.1) | 98.4 (98.2) |
まあまあ、合格率は低い。
過去問が変わってきている。電子制御向けにだ。ただ、これいるか?という問題が出た時はマジでビビったというか、おい・・・と思った。
【超重要!保存版】筆記試験を二回受けて気づいたこと
基本的には過去問が出る。
俺はここで気づいてしまった。過去問をやっているとき、ふとある法則が見えてしまったんだ。

おい、これ過去問見てたら5年おきで再利用されてるの多いぞ。
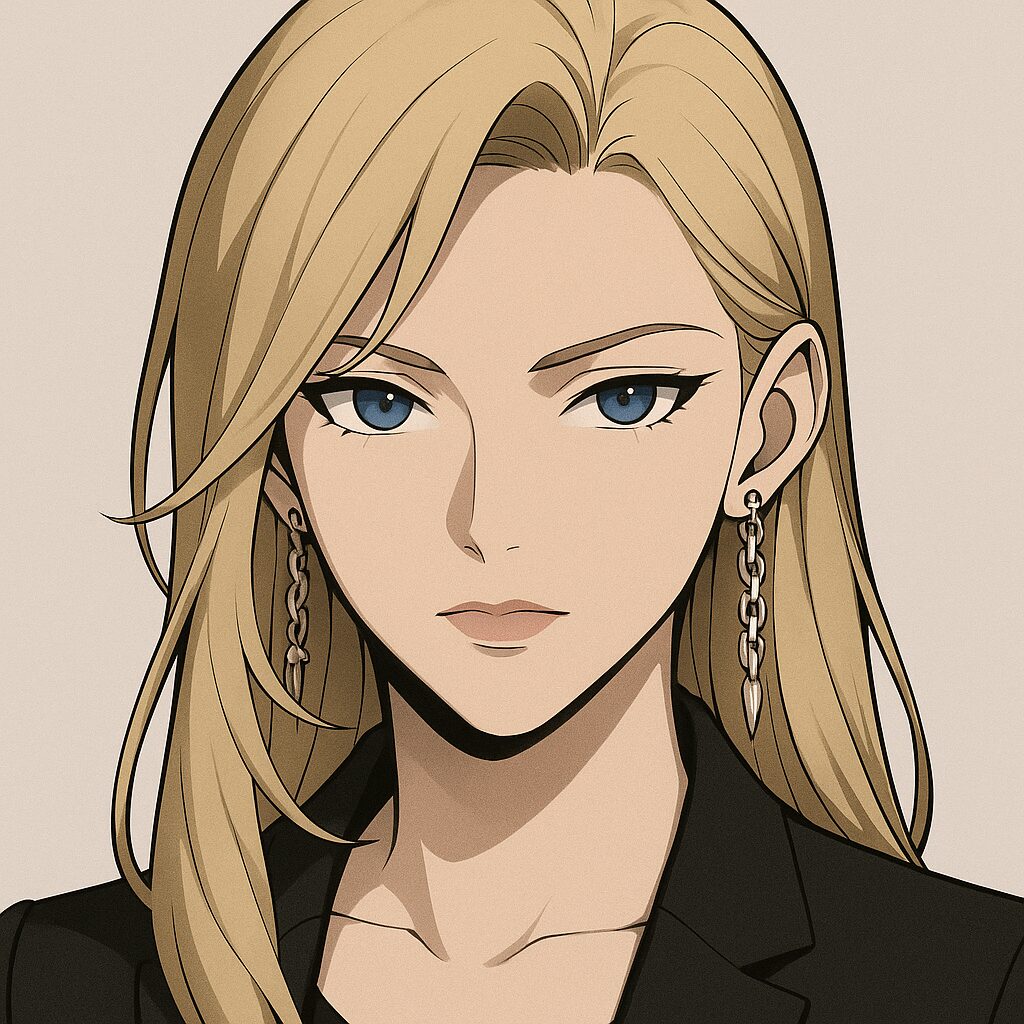
それで、ヴェルニスの予想は的中したの?

ああ、過去問を見て、次に受けるタイミングで5年目になる問題を重点的に解いて、試験日にバッチリあたった。
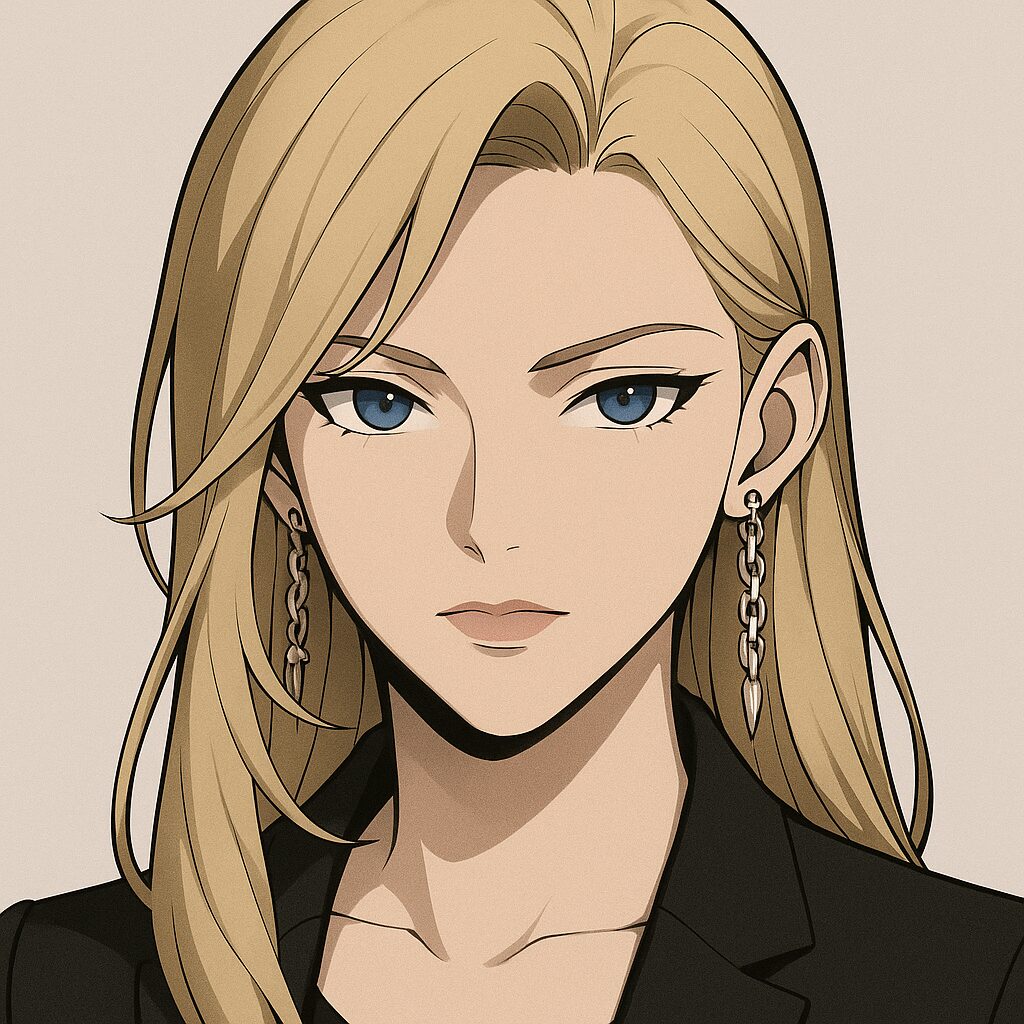
さすがはの気付きね。
そう、5年スパンで過去問が流用されていることに気づいてからは、新規で出てくる問題は無視しようという考えで、練習した。結果は合格だ。
学科試験が合格すれば、次は実技試験だが、俺は振興会の一級自動車整備士講習を受講していたから、実技免除だ。
つまり、残すは口述試験。
口述試験は何を問われるのか?
特に難しいことは問われない。試験管が質問をしてきたことに対して自分の考えを言うだけだ。
例えば、試験管が「最近、キーキー音がなるんですよ」と聞いてきたとする。受験者はそこから聞き取りして診断していく。
ブレーキか?と頭によぎっても答えは出さない。断言しない。
というのが続いて、最終的に受験者が
というような回答が出せればOK。
極端な上がり症出ない限りは、二級自動車整備士を持っている人なら実務で使っているお客さんとのコミュニケーションの範囲で合格する。
他にも、記録簿から読み取って、交換を勧めるとか、車の状態がどうとか話たりする。
求められる知識レベル
特に、環境と安全、法令に関しては5問ずつ出題されるが、これらは暗記問題になるため、すべて正解するのが鉄板だ。
1項目2つ落としてもOKだが、暗記だけだから落とすのは勿体ない。
それなら、計算問題の時間のかかるものを捨てる方が効率的。法令は最近だと、記録簿の保存期間とかを出すのにハマっているようだ。
今までの、ハイマウントが地上からどうのこうのというのは少なくなっている。
安全はハインリッヒさえ、覚えておけば、あとは実務でまともにやっていれば、自然とわかるものばかり。環境に関しては、一般常識さえ知っていればOKだ。
過去問を暗記さえすれば、このへんで落とすことはないだろう。
合格までに必要な期間と”俺がやった”効果的な学習法
【書籍の画像を貼る】
とにかく過去問だな。俺は公論出版の過去問と問題集をひたすらやっていた。
時間にしたら、覚えていないが、整備振興会の講習をすべて受講。
+毎日4時間は問題集を解き、土日は10時間以上問題を解いていたり、暗記したりしていた。俺の頭の悪さで、それくらいで、ギリ合格というレベル。
特に『和分の積』は使用頻度高いから覚えておくと良いのと、音に関してはとにかく復習だ。ハーシュネス、シミー、フラッタなどのHzを覚えること。
デシベルも覚える。この辺は短時間では大人の脳みそでは覚えきれないから、ひたすら暗記だ。
自動車整備士資格の取り方4つのルート
資格の取り方は一つではない。運転免許証と同じで、キミの学歴や現在の状況によって、最適なルートは異なってくる。ここでは、資格取得までの道のりを4つのパターンに分け、それぞれのメリット・デメリット、期間、費用を詳しく解説していく。
【図解:自動車整備士資格取得までの4つのルート比較フローチャート】
- 「最終学歴は?」「実務経験は?」などの質問に「Yes/No」で答えていくと、自分に合ったルート(A~D)がわかるチャートを作成。
- 各ルートの「最短期間」「費用の目安」「メリット・デメリット」をアイコンと共に表示する。
ルートA:最短・王道!養成施設(専門学校など)で学ぶ方法
まず、これが王道と言ってもいいだろう。
俺もトヨタ名古屋自動車大学校に2年間通い、二級自動車整備士となって就職した。
- 対象者:高校卒業後、未経験から整備士を目指す方
- 流れ:専門学校などに入学 → 卒業時に実技試験免除 → 学科試験に合格して資格取得
- メリット:体系的に学べる、実技試験が免除、就職サポートが手厚い
- デメリット:学費がかかる(2年間で約200~250万円)
- 1種養成施設と2種養成施設の違いとは?
上記内容をひとつずつ解説していく。
まず対象者のなるのは高校卒業する人。そして、未経験から整備士を目指す人だ。
俺の場合は高校を卒業してからすぐに専門学校に入ったが、外国人も大勢いた。中国人やブラジル人、県外から来る日本人。北海道から沖縄まで、わざわざドラゴンボールの作者鳥山明の事務所の近くの学校に通うために愛知県に来ていた。
年齢も幅広く、下は高卒者から上は40歳手前までの人がいた。もちろん、彼らも卒業してディーラーに就職していったし、国に帰って整備士をやるって人もいた。
つまり年齢に関係なく、未経験からゼロスタートで勉強して整備士になれるんだ。30代後半でも40代でも、知識がない状態で学習して試験に合格する。そして、学校からだと就職先が見つかる。
王道かつ、最短でほぼ確実になれる。
専門学校に入学するにはもちろん、試験がある。推薦をもらって入るとか、試験を受けて合格して入学する。そして、2年〜4年かけて自動車の勉強をする。その後、実技免除を受けて、国家試験に挑み合格する。晴れて自動車整備士資格を取得できる。
まず、学校では授業の流れ、カリキュラムがしっかり組まれている。特にメーカーが運営している自動車整備専門学校ならクオリティも高く、研修制度もしっかりしている。
さらに、就職先としてディーラーや、系列、傘下の企業へ就活できるというのもメリットだ。ネームバリューもあるため、ブランドとして活用することもできる。トヨタの学校を出た、日産の学校を出た、ホンダの学校を出た。という具合だ。
なんといっても、資金だろう。とにかく、専門の技術スキルを学ぶのはお金がかかる。おおよそ、2年課程で200〜250万円の金額が必要になってくる。奨学金制度を活用するといい。
あるいは、必死に頑張って入学金や学費の免除枠に自分を捩じ込むかだ。クラスメイトにいたが、やはり学費免除になる人間は学年1位の成績を常にキープしていた。上位5人くらいで成績勝負をしていたが、やはり桁違いにすごかった。
奨学金は基本的に誰でも低金利で借りれるが、卒業後に返済していかないといけない。
借りたものは返す。それだけだ。
また、強いていうなら俺の場合はトヨタ名古屋自動車大学校の学生証がクレジットカードと兼用だったため、カードを使いすぎて、支払い延滞、滞納などしてブラックリストになった者もかなりいた。
学生証にクレジットカード機能がついているとかなり困る。高校卒業したばかりのまだ、クレジットカードを持てない、カードの威力、恐ろしさを知らない人間がいきなり10万円の枠があるカードを持たされるんだからな。
これは提携していたカード会社と色々なメリットが学校側にあるんだろう。三○住○カードだったが。
この辺もデメリットになると思っている。
一種養成施設と二種養成施設との違い
さて、王道ルートに学ぶにしても、2つの種類が存在する。
専門学校と整備振興会などが行う技術講習などだ。
一種養成施設とは?
これは未経験、つまり実務経験がないものを対象とした自動車整備専門学校などを言う。
- 専門高校
- 短期大学
- 専門学校
- 職業能力開発校
などが挙げられる。例えば、トヨタ名古屋自動車大学校や日産学園、高山自動車短期大学や中日本自動車整備学校だ。
二種養成施設とは?
一方で二種の方は自動車整備振興会などが行う講習が該当する。
例えば、俺の場合は一級小型自動車整備士を取得する際に、すでに実務経験もあり、二級ジーゼルとガソリンを保有している。そこから、自動車整備振興会の行う一級小型自動車の講習に申し込み、約一年をかけて受講し、試験を受けた。
この、実務経験がある、なんらかの資格を保有している人に向けた講習が二種養成施設として扱われる。
ルートB:働きながら目指す!実務経験を積んで受験する方法
- 対象者:未経験から整備工場などに就職し、働きながら資格取得を目指す方
- 流れ:整備工場で実務経験を積む(3級なら1年以上) → 学科・実技試験を受験
- メリット:学費がかからない、給料をもらいながら学べる
- デメリット:受験資格を得るまでに時間がかかる、独学での勉強が大変、実技試験対策が必要
これもよく見るパターンだ。
特にディーラーにいる時によく見かけるが、専門学校を卒業して、二級ガソリン・二級ジーゼルを受け、どちらか一方しか合格しなかった場合。
ディーラーによっては、内定条件が変わってくるため、入社後に取得するように言われたりする。もちろん、どちらかでいいと言う会社もある。
この場合、落ちてしまった方の資格を取得するために、仕事をしながら実務経験と給料を手に入れ、仕事が終わったら独学で勉強する必要がある。これはデメリットになるが、独学で勉強するため、学費などはかかってこない。すでに専門学校で学んだことを次の試験まで忘れないように維持すればいい。
また、ガソリンスタンドで実務経験を積んで二級自動車整備士を取得する人も大勢いる。この記事を読んでいる人の場合、このルートも当てはまるだろう。
ルートC:大学・高校の機械科卒が有利に進める方法
- 対象者:機械に関する学科を卒業した方
- 流れ:卒業後、実務経験期間が短縮される → 学科・実技試験を受験
- 短縮される実務経験の期間を具体的に解説(例:機械科高校卒なら1年6ヶ月→6ヶ月に)
- このルートのメリットと注意点
これも意外といるのだが、工業高校を卒業してから専門学校には通わずに、自動車整備士の試験を受ける人がいる。実務経験もガソリンスタンドやオートバックスでのアルバイトで条件を満たしている学生も多い。
2025年7月に出された国土交通省のプレスリリースで、通った学校によって1年4ヶ月以上、1年以上という実務経験になった。
詳細は自動車整備士資格の実務経験年数の短縮についてを参照するといい。
ルートD:職業訓練校で効率的に学ぶ方法
- 対象者:離職者の方、キャリアチェンジを考えている方
- 流れ:公共職業訓練(ハロートレーニング)を受講 → 受験資格を得て試験に挑戦
- メリット:受講料が無料(テキスト代などは自己負担)、給付金を受け取れる場合がある
- デメリット:募集期間や定員が決まっている、誰でも受講できるわけではない
正直、このルートは条件を満たすのが少し厳しいかもしれない。職業訓練校の場合は厚生労働省の管轄になる。つまり、受講料などはゼロ〜数万、かかって十数万円だ。
失業保険なども条件を満たしていれば、受け取ることが可能。その場合はお金をもらいながら学ぶことができるのはメリットでもある。仮にパワハラで精神病になってしまい、異業種転職を考えて整備士を目指そうとする。
失業保険を受け取れる条件に当てはまる可能性が出てくるわけだ。また、受講給付金というのもあるため、このルートの場合は各自治体などにも確認するといいだろう。
そして、最大のデメリットとなるのが、定員人数だ。募集されている人数が限られているため、絶対に受講できるかと言うと、それはない。その点、注意が必要となる。
自動車整備士の資格に関するQ&A|よくある疑問をプロが解決
最後に、資格取得を目指す多くの方が抱く、細かな疑問についてQ&A形式で回答します。
- Q1.資格がなくても整備士として働けますか?
-
A.もちろんだ。無資格でも整備補助として働くことは可能だし、分解整備以外の作業は問題なくやっていい。もっと言うと、俺がブラック企業にいた頃に内部告発して、国土交通省と愛知運輸支局が監査に来た時に「認証取ってなくて、青空整備だったら、何やっても言われることはない」と言っていた。
つまり、認証も指定も取ってない、国から認可を受けていない町工場なんかは整備士の資格がなくても分解整備を行なっている。実際こういう工場は多い。
とはいえ、給料アップやキャリアアップを目指すなら、資格は必要となってくる。
- Q2.独学だけで資格を取得することは可能ですか?
-
A.当たり前だ。「できる or できない」ではなく、””やるか or やらないか””だ。
一般的にその道のプロフェッショナルになるには、1万時間学習が必要と言われている。
心理学者のアンダース・エリクソンという教授が、発見したもので、一流になるには1万時間の教育や練習をする必要があるとしている。いわゆる「一万時間の法則」と呼ばれているものだ。
とはいえ、独学での試験。特に実技試験への対策が難しいと俺は考える。学科はなんとかなるだろうが、実技試験に関しては実際にツールや計測器を用いて、実践してみないと、いざ初めて触るとなった時にうまく扱えないだろう。
- Q3.女性でも整備士資格を取得して活躍できますか?
-
A.もちろんだ。最近、いや、ここ数年の間に女性の整備士は増えてきている。俺が専門学校に通っていた時は学年に6人しかいなかったが、最近では女性が多くなってきており、専門学校のホームページの顔として使われるようになってきた。
一般的に男性の整備士からすれば、女性には優しく、重たいものや危険が伴いそうなものは、男性がサポートしてくれる。トルクが強いところも男性が問題なくサポートしてくれるため、その点は問題ない。
余談だが、以前スタビレーの工具を探していた時にたまたま見かけたインスタで、女性が航空整備士をやっていて、しかもモデル体型、美人で、工具はスタビレー一式だったのを見たとき、思わずカッコいいと思ってしまった。
だから、女性でも安心して整備士資格の取得を目指し、自動車整備士として活躍してほしい。
また、男性ばかりのギスギスした空気を和らげたり、コミュニケーション能力が高いことから、接客を重視している企業では重宝されることもある。
- Q4.資格取得後の将来性や年収はどうですか?
-
A.正直に答える。これに関してはなんとも言えない。俺を例えにするなら、愛知トヨタ自動車に入った時は、同じ整備士で同級生よりかなり給料はよかった。10万円以上差がつく友達もいたくらいだ。
そこから、転職したりして、トヨタ時代の給料からは大きく下がったり、実力を見せて一気に給料の水準をトヨタ時代に戻したりもした。
これは俺の考えになるが、給料が高いということだけを判断材料にすると、損をしたり、痛い目を見ることがある。やはり、一緒に働く仲間だったり、福利厚生の充実度が最終的に求められる。
若いうちはあまりそういうことは考えないかもしれないが、家族ができたり、歳をとってくると、そういったことが気になってくるようになる時期が訪れる。
オマエがそうならないように、俺のブラック企業人生ストーリーを参考にしてほしい。
まあ、ビビらせてしまったが、自動車技術はEVや自動運転など常に進化しており、対応できる専門知識を持った整備士の需要は今後ますます高まる可能性はある。特に一級資格や特定整備に関する知識を持つ人材は市場価値が高く、年収アップに直結するはずだ。
直近では、2025年に整備士の資格制度の見直しや工賃の改善などで、今後の整備士の処遇が改善されていくことが匂わされている。
- Q5.どの資格から目指すのがおすすめですか?
-
A. まずは実務の幅が広がる「二級自動車整備士(ガソリンまたはジーゼル)」を目指すのが一般的。高校生の方や、まず基礎から固めたい人は「三級自動車整備士」からのステップアップも良いかもしれないが、実用的ではないことに懸念点がある。
ここまで読んでくれてありがとう。
この記事では自動車整備士の資格について、種類から難易度、そして具体的な取り方までを網羅的に解説してきたつもりだ。
- 資格には1級・2級・3級・特殊整備士があり、中心となるのは「二級」であること。
- 難易度は3級が最も易しいが、段階的にステップアップが必要であること。
- 資格の取り方には大きく4つのルートがあり、自分の状況に合わせて選ぶべきであること。
自動車は人々の生活に欠かせないインフラであり、その安全を守る自動車整備士は、AI時代が来ても決してなくならない社会的意義の大きな仕事。技術の進化と共に、整備士に求められるスキルは変化してくるが、それは同時にキャリアアップのチャンスでもある。
この記事が、キミの夢への第一歩を踏み出すための、確かなロードマップとなれば、これほど嬉しいことはない。
まずは君に合ったルート(専門学校の資料請求、求人情報の検索など)から、具体的な行動を始めてみてくれ。未来の自動車業界は、オマエを待っている!

